何回説明しても相手に伝わらないといった経験をしたことがある人は多いと思います。
仕事でもプライベートでも、このようなことはあると思います。
時には「もう何回目だろう…」とため息が出たり、「なんでこんな簡単なことがわからないんだろう」と苛立ってしまうこともありますよね。
この“伝わらない現象”は、単に「相手が理解力不足だから」だけでは説明できません。そこには伝える側と受け取る側、両方の心理やコミュニケーションスキルが関係しています。
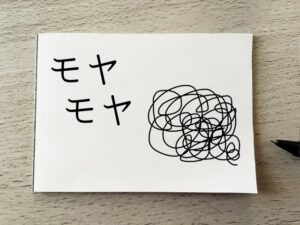
〇伝える側の心理とスキルについて考えてみましょう。
伝える側が無意識にやってしまうのは、「自分の頭の中の地図をそのまま相手に渡せる」と思い込んでしまうことです。しかし、相手の知識量や背景、使う言葉の意味は人それぞれです。自分の基準だけで説明してしまうと、相手にとっては断片的であり意味不明な言葉の羅列であったりします。
「これくらい知っているだろう」という前提で、専門用語を多用してしまったり、全体像やゴールを伝えずに細部だけを話すことで結論が見えない説明になっていたりします。また、相手の反応を確認せず、話し続けてしまうことで一方的な情報を投げかけているだけということになったりします。
心理的には「ちゃんと説明している自分」という自己満足感が働きやすく、相手の理解度チェックが後回しになりがちになっているわけです。
〇受け取る側の心理とスキルについて考えてみましょう。
受け取る側には「理解の障壁」というものがあります。説明の土台となる基礎知識がないため、話がかみ合わなかったり、「ここが分からない」と言えず、曖昧なまま聞き流してしまったり、「この人の説明は難しい」と思い込むことで、理解モードに入れずバリアを張ってしまったりします。
特に、受け手側が“恥ずかしさ”や“立場上の遠慮”で質問できない場合、わからない部分が放置され、回を重ねても理解は進まなくなってしまいます。

この「伝える側は説明しているつもり、受け取る側はわかったふり」という構図が、説明ループを生みます。伝える側は「こんなに説明したのに!」と感じ、受け取る側は「また同じことを言われた…」と感じる。実はお互いに不満を溜めながら、平行線のまま時間だけが過ぎていっているのです。「分からないと言っても大丈夫」という空気がなければ、受け手は沈黙を選んでしまい、伝え手はそれに気づかないままになります。心理的すれ違いが発生してしまうのです。
では、どうすれば「何回説明しても伝わらない」状態を防げるのでしょうか。
〇伝える側ができること
・「何を」「なぜ」説明するのかを最初に伝え、全体像を提示する
・「ここまでで質問は?」を入れ、相手の理解度を確認しながら進める
・理解した内容を自分の言葉で説明してもらう
〇受け取る側ができること
・「ここが分からない」を明確に伝え、具体的な質問をする
・「つまりこういうことですね?」と確認し、要約を返す
・事前に調べる努力をして、理解に必要な背景・知識を補う
このような配慮ができると大分変ってくるように感じませんか?
次回は、誤解やすれ違いを減らす近道について触れてみたいと思います。










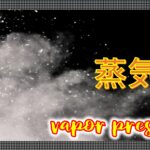







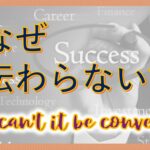
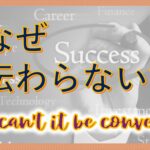
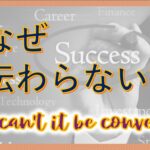
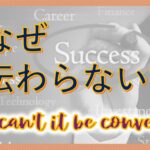








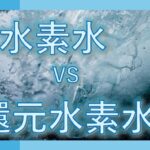




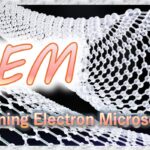
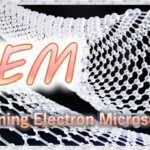
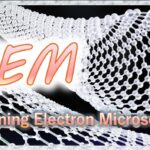








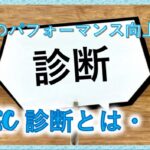
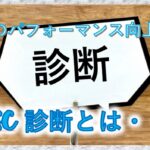




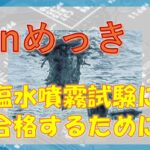
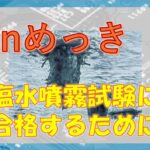
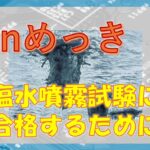












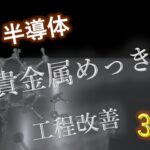
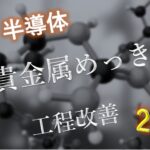
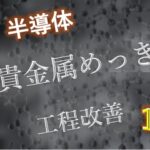
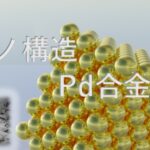
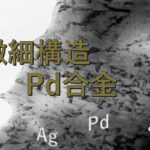

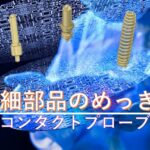














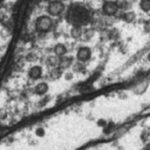

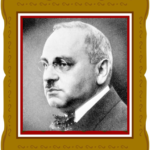




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
 FlabR(フラバー)について
FlabR(フラバー)について