前回は、伝える側と受け取る側、両方の心理やコミュニケーションスキルの関係についての内容でした。
今回は、伝わらないの心理的要因ついて触れてみたいと思います。

私たちはつい「ちゃんと説明すれば、相手もわかってくれるはず」と思いがちです。家庭や職場…どこでも「話せばわかる」というフレーズを耳にしますが、現実はどうでしょうか?むしろ「何回も話してるのに、なんで伝わらないの!?」と感じる場面のほうが多いのではないでしょうか。
「話せばわかる」という考え方の裏には、「自分の言葉は正確に相手に届く」 「相手は自分と同じ理解をする」という前提があります。しかし、実際にはこの前提が成り立たないことがほとんどです。言葉の意味は人によって微妙に異なり、同じ言葉でも背景や経験によって受け取り方が変わってきます。
「話せばわかる」というのは、実は一方向のコミュニケーション前提の考え方です。しかし、本当に理解を共有するには、一方的に話すだけではなく、お互いの理解を確認しながら進める必要があります。つまり「話せばわかる」ではなく、「一緒にわかる」ことを目指すことが大切になるのです。
「話せばわかる」という言葉に対して、信じたい気持ちはわかりますが、残念ながらそれは“幻想”かもしれません。むしろ、説明は相手の世界観に合わせて橋をかける作業であり、一方的な情報伝達ではなく、双方が歩み寄る“共同作業”として捉えたほうが、結果的に「伝わる説明」になるのです。

誰かに何かを説明していて、ふとこんな気持ちになったことはありませんか?
「どうして伝わらないんだろう…」「ちゃんと言ったのに、なぜ違う理解をされるんだろう…」
この現象の裏側には、単なる理解不足や記憶力の差だけではなく、人間の認知のクセや心理的要因が深く関わっています。
次回は、誤解やすれ違いを減らす近道について触れてみたいと思います。










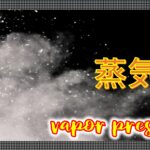







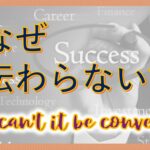
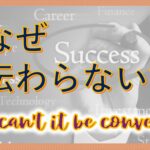
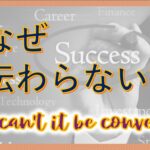
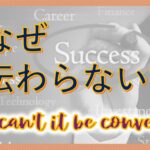








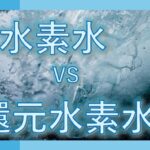




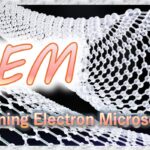
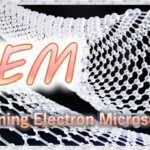
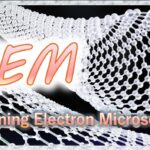








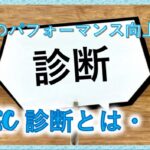
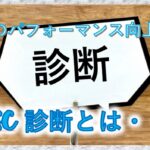




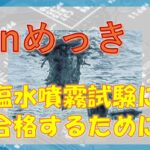
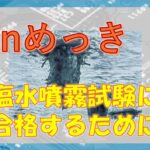
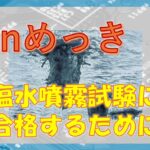












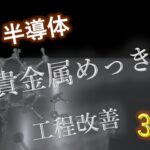
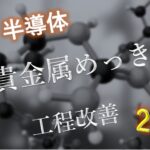
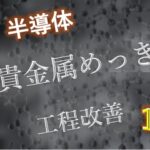
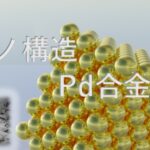
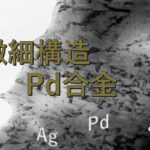

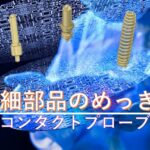














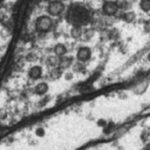

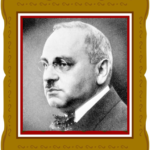




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
 FlabR(フラバー)について
FlabR(フラバー)について