「金めっき」と聞いて、どのようなめっきでどのようなところにめっきされているか知っているでしょうか?
意外と近くにあったりするのですが、気がつかなかったり、または気にもしていないかもしれません。
今回は、金めっきについて触れてみたいと思います。

最初に、金は価格が高いという印象を持っていると思いますが、いくらくらいかご存じでしょうか?
金の相場は非常に高く、2025年10月に1グラムあたり23,000円を超えました。ビックリしますね。
1gの重さはどのくらいかというと、よく1円玉1枚の重さで例えられます。大きさによりますが、米粒で約20粒くらいの重さです。しかし、金は密度が高い金属なので、1円玉のような大きさにはなりません。
金の体積 = 重さ ÷ 密度 = 1 g ÷ 19.3 g/cm³ ≒ 0.052 cm³
1円玉は、直径20 mm、厚さ1.5 mm、体積は約0.47 cm³ なので、 金で同じ大きさの1円玉を作ると約9 gになります。よって、金1gは1円玉の約1/9の体積に相当することになります。
米粒は、普通の1粒の体積は0.02〜0.03 cm³程度などで、 金1gは米粒 2粒分くらいの体積に相当することになります。米2粒の大きさで23,000円です。高く感じますよね。

ここで、金の歴史について触れてみたいと思います。
金(Au)は人類史において特別な価値をもった金属でした。古代から現代に亘り、装飾品や通貨、工業材料として広く利用されてきました。
私は、金に対して古代エジプトのツタンカーメンを想像してしまいます。あれだけの金をどのようにして集めたのか謎です。一説には、ナイル川から砂金を採取して、ファラオに献上していたということです。この金がなぜ喜ばれたのかは、金特有の美しい輝きや金の不変性(化学的安定性)によるものです。
金の希少性や美しい輝き、化学的安定性は、文明の発展と共に常に価値を持ち続け、人々の経済活動や文化に大きな影響を与えてきました。現代では、金は装飾品としての材料に留まらず、エレクトロニクスや航空宇宙、医療分野に至るまで広範な用途で活用され、その需要は依然として増加傾向にあります。

このような金を「金めっき」として、金の特性を薄膜で活用する技術として「金めっき」は極めて重要な存在になります。電子部品の接点や半導体パッケージ、光学部品に至るまで、耐食性や導電性を確保するために金めっきが施されています。薄い膜であっても金の優れた特性を表面に付与できるため、資源的にも経済的にも効率の良い利用方法といえます。
次回は金の歴史についてもう少し踏み込んでみたいと思います。










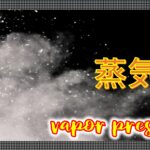







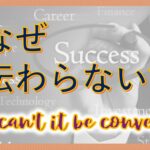
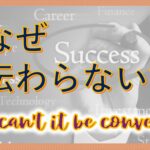
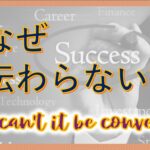
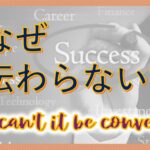








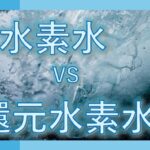




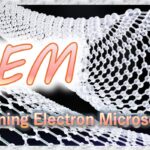
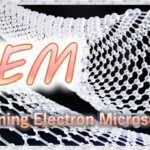
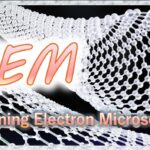








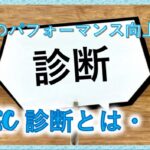
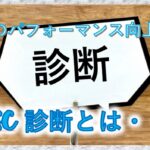




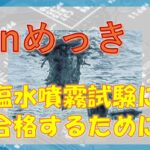
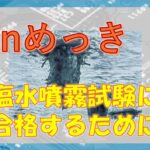
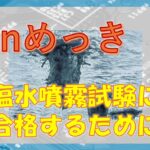












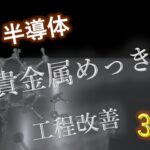
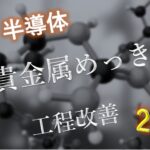
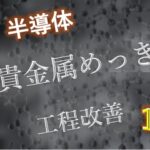
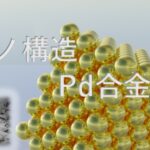
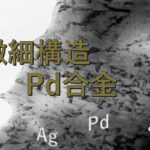

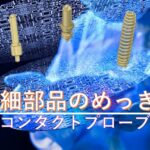














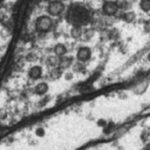

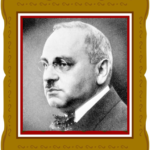




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
 FlabR(フラバー)について
FlabR(フラバー)について