今回は「拡散」についての内容になります。我々の仕事においては、常に考えさせられる内容であるので、取り上げてみたいと思います。
拡散とは、どのような現象のことをいうのでしょうか?

コップの水に、1滴のインクを垂らすと、かきまぜなくてもいつのまにか広がって全体を色づけるような状態を経験したことがあると思います。また、部屋の片隅に置かれた花の香りやアロマの香りは、かなり離れた所まで漂ってくると感じたこともあるでしょう。このような現象は液体や気体では巨視的な流れがなくても分子の移動が起こっているのであって、つまり拡散が起こり、お互いに混ざりあうことを示しています。
我々は、このような拡散現象を感覚的に理解することができます。一方、固体の拡散現象は気体や液体中に比べれば、はるかに起こりづらいので検出することは容易ではありません。
「拡散」の歴史について少し触れてみたいと思います。
1896年、イギリスのRoberts-Austenは固体鉛中でも金が拡散することを発見しました。これが固体金属中での最初の拡散の研究であると考えらています。Roberts-Austenは、1843年イギリスSurry州のKenningtonに生まれました。Roberts-Austenの主な業績は①オーステナイト相に関わる研究、②金属の機械的性質、③合金組成の分析法の改良、④熱電対を用いた炉や溶融金属の温度の測定法の確立などがあります。オーステナイトは彼の名にちなんでいるわけです。

熱力学のボイル・シャルルの法則で有名なイギリスのRobertBoyleは、物質には最小単位の物質種と同じサイズのボア(孔)が存在し、そのボアと物質種が交換することによって固体物質の内部でさえも物質移動(拡散)が起こっているというもので、原子という概念もない時代に固体内に空孔が存在すること、そして原子の拡散が空孔機構によって起こっていることを示唆した画期的な論文を発表しました。
1820年には、FaradayとStodartは、融点以下の温度で、白金が鋼と固相接合できることを見い出し、それが拡散によって起こる合金化であるという考えを提案しました。
1864年には、Grahamは物質の三態(固体・液体・気体)は、通常いかなる液体や固体にも存在し、固体と言えども一部に粘性の低い液相や気相があるために金属同士がお互いに拡散し合うことができ、固相接合が可能であるとの考えを発表しました。そして、Sringは、鉛と錫とを溶解凝固させた後も引き続き活発な分子運動が起こり、新しい中間相が生成されるという考えを提案し、固体中にも液相や気相が共存するというGrahamの説を支持したそうです。
このような偉大な発見は、本当に興味深く、尊敬してしまいます。
次回は金属の腐食・酸化と拡散の関係について触れてみたいと思います。










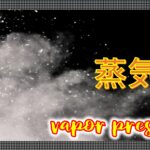







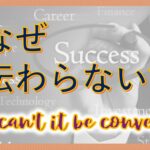
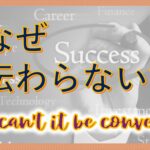
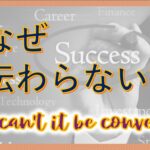
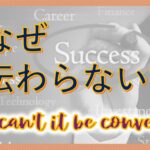








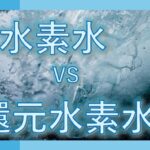




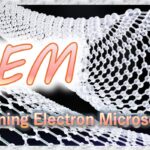
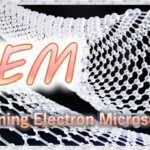
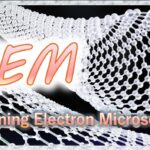








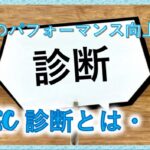
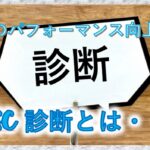




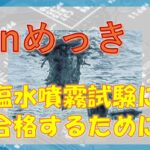
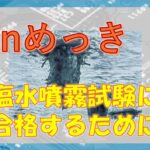
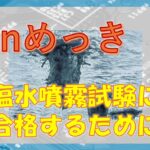












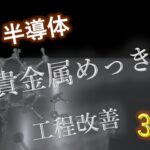
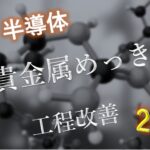
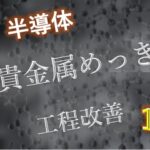
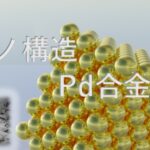
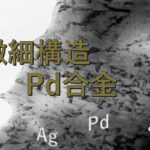

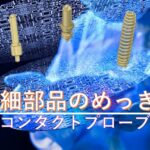














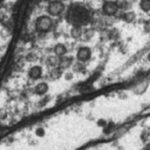

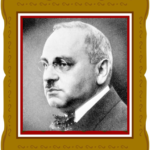




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
 FlabR(フラバー)について
FlabR(フラバー)について