前回は、金の価値について、歴史を含めて紹介しました。
今回は、金の歴史についてもう少し踏み込んでみたいと思います。
金の歴史的意義として、掘り下げてみます。
これまでに説明したように、金が利用されだしたのは紀元前数千年にまで遡ります。
古代エジプトでは装飾品や宗教的儀式に不可欠であり、古代ローマでは通貨として広く流通しました。
中世ヨーロッパでは、金の産出を巡る争いが国家間の戦争を誘発することもありました。
さらに近代以降、金本位制の確立により、金は世界経済の基盤として機能してきました。

金は単なる装飾品や通貨としての役割だけでなく、人類の宗教・権力・科学技術の発展に密接に結びついてきたのです。その歴史的意義について、もう少し掘り下げてみましょう。
古代文明では、金は「不滅」「神聖」を象徴する存在でした。
古代エジプトでは、ファラオの墓から発見される副葬品の多くに金が使われていました。特に有名なツタンカーメン王の黄金のマスクは、死後の世界で永遠に輝く存在を象徴していました。金は「太陽神ラー」の肉体の一部と信じられ、王権の正統性と結びつけられていました。
インカ帝国では、金は「インティ(太陽神)の汗」と呼ばれ、神聖な儀式や神殿の装飾に使われました。しかし、装飾ではなく宗教的象徴が主目的であり、通貨や交易にはほとんど使われませんでした。聖書においても、金はしばしば神殿や聖具の素材として登場しています。
このように、金は「経済的価値」よりも先に「精神的価値」として人類社会に根付いたという点が興味深いところですよね。

金はしばしば国家の繁栄や衰退を左右する存在でもありました。
大航海時代(16世紀)、スペインは中南米から大量の金銀をヨーロッパに持ち帰りました。これにより一時的に莫大な富を得ましたが、同時に「価格革命」が起こり、ヨーロッパ全土で物価が急騰し、結果的にスペイン経済は不安定化し、長期的には国家財政の破綻を招いてしまいました。
19世紀後半には、イギリスを中心に「金本位制」が確立され、各国通貨の価値が金に裏付けられる時代が訪れました。これにより国際貿易の安定性が増し、世界経済のグローバル化が加速しました。
古代において、金が科学実験材料として使われていたことも非常に興味深い点です。
中世ヨーロッパや中国の道教では「賢者の石」や「仙薬」を得るために金が追求されていました。実際に金自体は不老不死の薬として用いられることもあり、中国の始皇帝が服用したという記録もあるそうです。
20世紀初頭、ラザフォードらが行った原子核散乱実験では、薄い金箔にα粒子を当ててその散乱挙動を解析し、原子核の存在を証明しました。この発見は原子物理学の基礎を築くものであり、金は科学史における「鍵の素材」ともいえるものでした。
現代では、金の価値は「装飾品・金融資産・工業材料」の三本柱に基づいているようです。特に工業用途における利用は年々拡大しており、電子部品や半導体分野での金めっきは不可欠です。
さらに近年では、再生可能エネルギー、電気自動車、5G通信などの分野でも金の需要が拡大しており、持続可能な供給体制が課題となっています。
次回は、金の特性や性質などについて触れてみたいと思います。










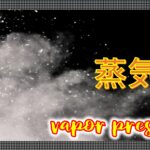







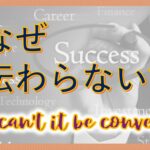
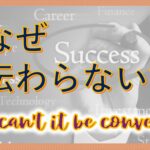
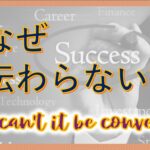
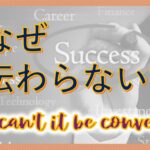








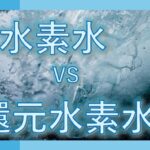




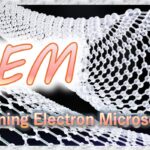
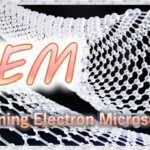
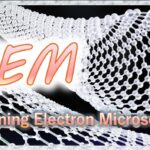








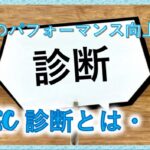
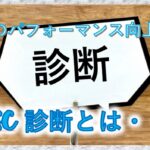




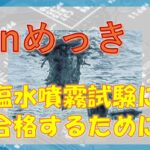
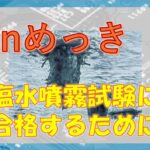
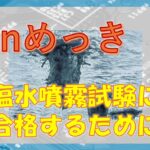












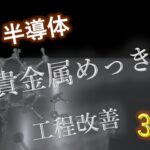
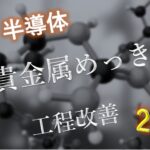
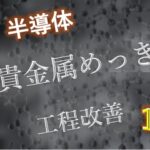
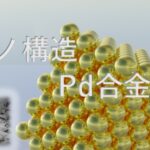
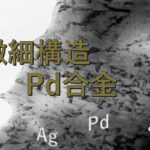

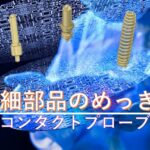














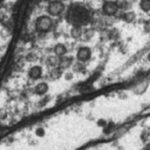

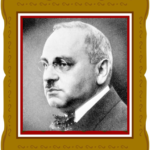




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
 FlabR(フラバー)について
FlabR(フラバー)について