パワーハラスメントの2回目になります。
前回は経験談を含めてパワハラについて記しました。
職場内でのパワハラには、どのようなものがあるか考えてみたいと思います。
言葉でのパワハラは職場内でよく見かける光景です。
上司が部下に対して、日常的に侮辱的な言葉を投げかけたり、失敗を過度に責めたりするケース。
これにより、被害者は自尊心を失い、精神的なダメージを受けることが多いです。
過剰な仕事を押し付けるパワハラも多いのではないでしょうか。
上司が特定の人にだけ不必要に多くの仕事を押し付けたり、無理な納期を設定したりすることで、被害者に過度なストレスを与えるケース。
孤立化させるパワハラもよくある内容ですね。
特定の従業員を意図的に職場で孤立させ、会議や情報共有から排除するケース。
これにより、被害者は不安感や疎外感を感じ、職場への不信感を抱いてしまいます。

私が受けたパワハラの一つに孤立化がありました。
第1話に出てきた役員である上司によるものでしたが、上司自らの方針で始めた活動は、実績が出ないことやトラブルの回避が上手くいかなった結果となりました。
この結果に対し、保身のために、その責任を部下に押し付け、事実を捻じ曲げたのです。
自身に責任の目が向かないようにするために、情報が流れないようにした上で重大な会議に出席させ、あたかも仕事をわかっていない状況や仕事ができていない状況を作り、疎外感を与え、周りから排除されるように姑息な根回しをする行動をしていました。
それは傍から見ても明らかにわかる行為だったのですが、役員という権限を利用した悪質な行為により、部下達も保身にまわり従ざるを得なかったのです。
その結果、組織は目に見えないところでおかしくなり、数名が鬱病を発してしまったのです。
それでも、パワハラした本人は自覚がなく、相も変わらず仕事を継続していました。
職場内のパワハラでよくあるケースはこのようなものであると思いますが、他にもあるでしょう。
ここで
パワハラをする側の心理面をいくつかの視点からみていきたいと思います。
パワハラを行う人は、職場での権力や優位な立場を利用し、他者を支配しようとする欲求が強い傾向があります。
これは、次のような心理的背景から生じることが多いです。
役職や地位に対する強い執着心があり、それを他者に誇示することで自己肯定感を得ようとする心理。
上司やリーダーの立場にある場合、自分が権力を持っていることを示すために、部下に対して威圧的な態度を取る傾向があります。
他者をコントロールすることで、自分が安全であり続けようとするのです。
自分の指示に従わない部下や同僚を排除したり、罰することで、自己の優位性を得ようとする心理が働きます。

パワハラを行う側は、内面的に不安やストレスを抱えていることが多く、それを他者に対する攻撃的な行動で発散しようとする傾向があります。
特に、上層部からの圧力が強い場合、そのストレスを部下に転嫁し、厳しい指導や攻撃的な行動で解消しようとします。
自分が管理職やリーダーとしての期待に応えられていないという不安が他者への攻撃性として表れます。
また、職場以外でのストレスや不安を職場で発散することで、自分の感情をコントロールしようとするケースもあります。
このような場合、攻撃的な行動は問題を解決する手段ではなく、感情のはけ口としているのでしょう。
パワハラを行う人は、実際には自分に対して自信がなく、それを他者に対する攻撃で補おうとします。
私の場合も同様で、役員自らが行動して示すことができないタイプの人だったので、自信のないところを周りに悟られないように行動する人でした。
気も小さいタイプなので、会社の中で自分を大きく見せたいタイプです。
だからこそ権力欲しさに、手段を選ばず役職を手にしたのでしょう。
このように、自分に自信がない人は、他者を攻撃することで自分の優位性を示し、劣等感を隠そうとする心理が働きます。
他者をおとしめることで、自分が優れていると感じたいという欲求がパワハラの一因となっているのでしょう。
次回はパワハラの心理面についてもう少し触れてみたいと思います。










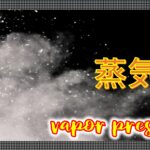







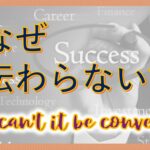
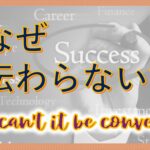
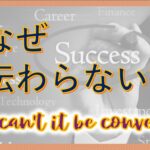
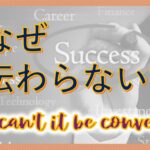








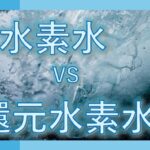




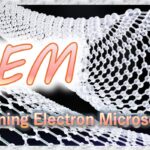
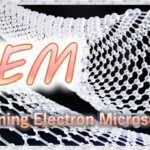
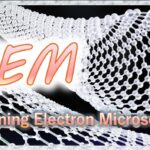








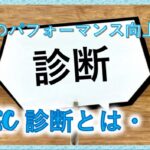
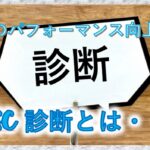




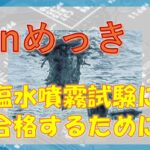
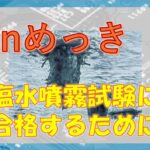
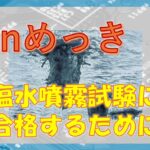












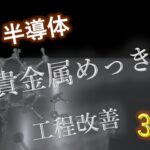
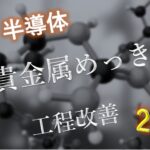
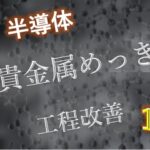
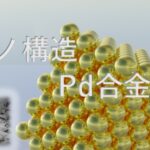
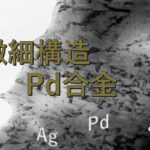

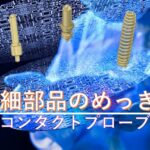














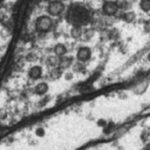

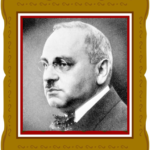




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
 FlabR(フラバー)について
FlabR(フラバー)について