前回は、伝わらないの心理的要因ついての内容でした。
今回は、誤解やすれ違いを減らす近道について触れてみたいと思います。
私たちは「理解」という行為について、そもそも二つの大きな勘違いをしがちなのです。ひとつは、情報は相手に正確にコピーされるという思い込みがあります。実際には、私たちの脳は受け取った情報をそのまま保存することはなく、自分の経験や感情のフィルターを通して無意識に加工してしまうのです。
もうひとつは、一度理解したらその理解は固定されるという思い込みです。しかし記憶は流動的で、時間の経過や新しい情報の影響を受け、容易に書き換わってしまうのです。

しかも、この理解の揺らぎをさらに複雑にしているのが「視点の偏り」にあります。人は全ての情報を公平に見渡すことはできず、興味や関心に合った部分だけを優先的に拾ってしまう傾向があります。さらに厄介なのは、専門性が高い人ほど、この視点の偏りが強まるということです。
専門知識を持つ人は、無意識に「相手も自分と同じ基礎知識を持っているだろう」と想定してしまいがちで、その結果、説明の中に前提の飛躍や専門用語の乱用が生まれます。例えば、化学系エンジニアが何気なく使う「モル」という言葉も、別の職種の人にとっては理解不能な言語に過ぎません。このように、伝える側と受け取る側の間に目に見えない知識の壁が築かれてしまうのです。
さらに、この壁を乗り越えたとしても、記憶というものは感情やその後の経験によって常に上書きされ続けます。同じ説明を受けても、相手が置かれた状況や感情状態によって、その解釈や記憶の形は全く異なります。だからこそ、「以前話したはずなのに覚えていない」「内容がすり替わっている」ということが日常的に起こっているのです。
そして極めつけは、人間が持つ認知バイアスです。相手に対して「この人の話は難しい」という先入観や、「このテーマは面倒くさい」という印象があると、それだけで脳は情報を受け取る前からシャットアウトしてしまいます。つまり、理解の障害は説明の内容だけでなく、その前段階の心理的ハードルにも潜んでいるわけです。難しいですね。

こうして考えると、「話してもわからない」状態は、単なる聞き手の怠慢や説明の下手さではなくて、理解の構造そのものに内在するズレや歪みから生じていることになります。本当に伝えるためには、用語の意味や前提をすり合わせ、目的やゴールを共有するなど、理解の土台を整える作業が欠かせません。相手と同じスタート地点に立ってから話し始めることが重要。それが、誤解やすれ違いを減らす唯一の近道になるのです。
次回は、コミュニケーション力のエッセンスについて触れてみたいと思います。










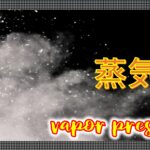







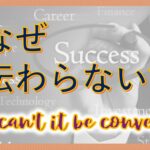
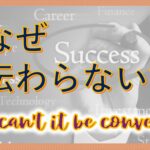
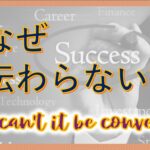
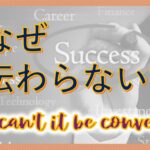








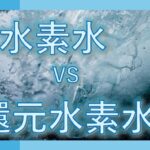




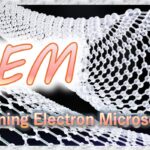
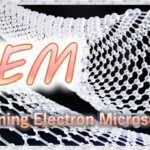
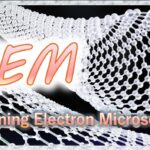








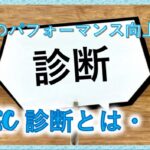
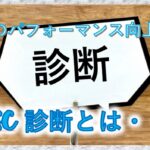




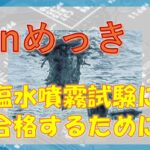
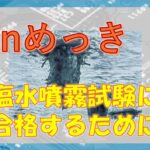
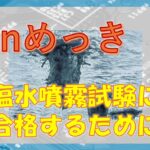












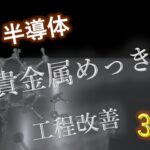
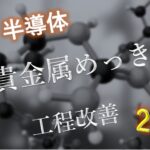
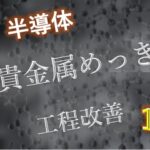
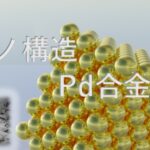
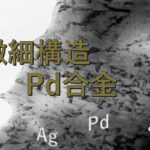

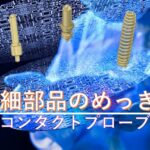














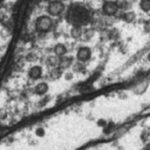

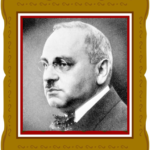




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
 FlabR(フラバー)について
FlabR(フラバー)について