前回の「ブラック企業」の3話目になります。
今回はブラックと思っていない企業などについて触れてみたいと思います。
会社としての強い仲間意識を作るため「チーム〇〇」といったような活動をすることがよくあります。これは、社員が会社に依存する傾向を強くすることに効果があります。
「仕事がすべて」
「努力すれば報われる」
といった価値観を社員に植え付けていくのです。
社員は「会社のために頑張ろう」という愛社精神が大きくなっていき、「自分が犠牲になってでも会社を支えるべきだ」と感じるようになります。

しかし、社員がどのように、どれだけ受け入れたかの度合いにより企業文化がつくられていき、流れでブラックといわれる企業文化ができていってしまうことがあります。
ブラック企業といっても、本当に悪質なブラック企業と経営者が全くブラックと思っていないブラック企業があると考えます。この二者の違いについて考えてみたいと思います。
悪質なブラック企業とはどのような特徴があり、社員はどのように感じているのでしょうか?
悪質なブラック企業の経営者は、当然のことながら自社の労働環境が過酷であることを十分に理解しています。利益追求のために、社員を使い捨てのリソースとして扱い、長時間労働や過剰な業務量を強要します。
倫理的な配慮が欠如しており、法的な義務を無視したり、従業員の権利を軽視しています。労働者の権利に対して無頓着であり、従業員が不満を訴えても改善を行うことはありません。
社員は長期間にわたって精神的・肉体的なストレスにさらされることが多く、結果として不安や恐怖を抱くことになります。
職場を辞めたくても心理的、経済的な理由で辞めることができず、無力感や絶望感に苛まれます。仕事に対するモチベーションが完全に失われ、疲弊し切った状態です。
最終的には、精神的な病気に発展することもあり、離職を強いられる場合もあります。
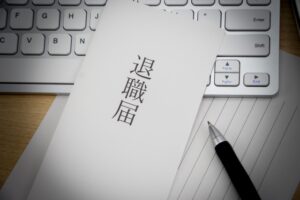
経営者が全くブラックと思っていないブラック企業はどうでしょうか?
このタイプの経営者は、自社の労働環境が過酷であることに気づいていないか、気づいていてもそれが「普通の経営」と考えています。
社員に悪影響を及ぼしているとは思わず、「社員に努力を求めることは当たり前」「この程度はどの会社でも同じ」と信じています。
自社が「業界の常識」として長時間労働や短納期があたりまえであれば、自社の労働環境がブラックなものであると気づかないまま、過酷な環境を継続してしまうでしょう。
このタイプの企業で働く社員は、経営者の善意や期待に応えようとする一方で、過剰な負担に疲弊しています。しかし、経営者が悪意を持っているわけではないため、従業員は「この状況は仕方ない」と諦める傾向があります。そのため、疲労やストレスが蓄積しても、改善を求めることをためらったり、現状を受け入れざるを得ない心理状態になります。
一部の従業員は、「自分が頑張れば報われる」という希望を持って働き続けますが、現実とのギャップに挫折感を覚えます。
そして、長期間にわたり努力が報われない場合、精神的なストレスが進行します。場合によっては離職に追い込まれてしまいます。
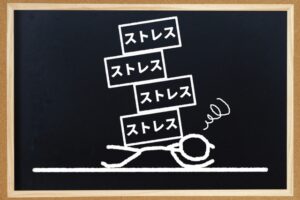
「悪質なブラック企業」と「ブラック企業と認識していないブラック企業」との違いは、経営者が意図的に労働者を搾取しているか、無意識のうちに過酷な環境を作り出しているかにあります。
認識していないブラック企業では、善意があるものの無知やリソース不足が問題の根底にありますが、悪質なブラック企業は利益を優先し、労働者を犠牲にしても構わないという冷酷な考えがあります。
社員の精神的な面では、認識していないブラック企業では、従業員は希望と諦めの間で揺れ動きますが、悪質なブラック企業では、ストレスと恐怖、絶望に苛まれることが多くなります。
どちらのケースも、社員のメンタルに深刻な影響を与えるのは間違いありません。
「ブラック企業と認識していないブラック企業」に勤務し、先に書いたような心理状態から自分を犠牲にしているのかどうかを考えてみることは、これから先の社会生活において大変重要なことです。大切なのは、自分であり、体が資本なので、早く気付くことができ、次の行動に踏み出すことだと思います。
悪質な労働環境やこのような社会がいつか一掃され、ストレスのない会社生活が実現することを願います。










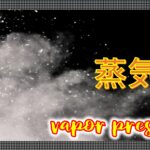







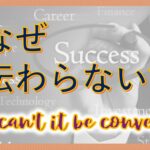
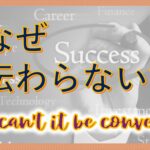
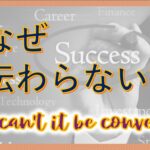
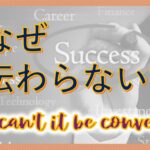








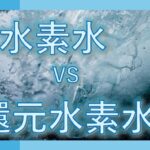




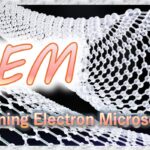
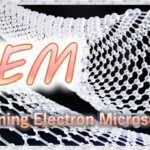
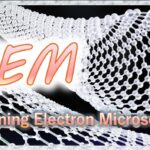








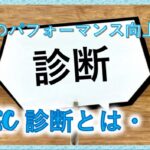
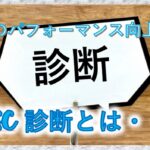




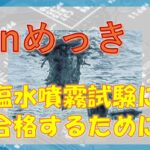
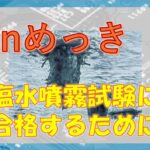
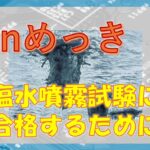












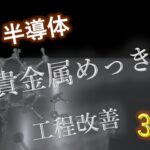
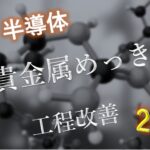
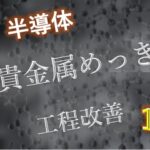
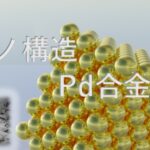
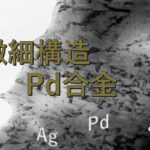

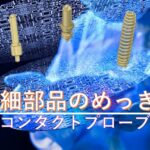














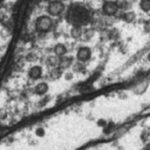

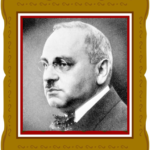




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
 FlabR(フラバー)について
FlabR(フラバー)について