前回は、鍛冶屋の歴史について触れてみました。
今回は、鍛冶屋で行われていた鉄の加工技術について触れてみたいと思います。
鉄の加工技術は古くから行われていますが、どのような方法があるのかを少し掘り下げてみたいと思います。

鍛造という加熱加工があり、「熱間鍛造」や「冷間鍛造」という言葉をよく耳にします。「熱間鍛造」は、鉄を800〜1200°Cの赤熱状態に加熱し、槌やハンマーで叩いて成形する方法です。「冷間鍛造」は、常温で塑性加工する手法で、強度が増す反面、加工硬化により割れやすくなるデメリットがあります。日本刀のような構造は、折り返し鍛錬によって不純物を除去し、均質な鋼を得るところが優れた技術になっています。
溶接や接合といった技術も重要であり、古典的には「鍛接」と呼ばれる、鉄を赤熱させて重ねて叩きつけ、分子レベルで融合させる方法です。現代では電気溶接やガス溶接という技術に置き換わっていますが、鍛接技術は伝統工芸においては、今も継承されています。
焼入れ・焼戻しという熱処理技術もよく耳にします。鉄を高温で加熱し、急冷(焼入れ)して硬度を上げた後、再加熱(焼戻し)して粘りを持たせる方法です。この技法により、「硬さ」と「靭性」のバランスを調整可能としているのです。
鉄の種類について、どのようなものがあるでしょうか
以下に簡単にまとめてみました。
| 鉄の相(相名) | 記号 | 温度範囲(℃) | 結晶構造 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| α-フェライト | α-Fe | 室温 ~ 約 912℃ | 体心立方構造 (BCC) |
磁性あり(〜770℃)、軟らかく延性あり。常温の鉄。 |
| γ-オーステナイト | γ-Fe | 約 912 ~ 1394℃ | 面心立方構造 (FCC) |
高温相。炭素を多く固溶できる(最大2.1%程度)。磁性なし。 |
| δ-フェライト | δ-Fe | 約 1394 ~ 1538℃ | 体心立方構造 (BCC) |
α-Feと同じ構造だが高温。溶融直前の固相。 |
| 液体(溶融鉄) | ― | 約 1538℃ 以上 | ― | 鉄が融解して液体状態になる。 |
このように大きく分けることができ、熱処理の温度で結晶構造の違う鉄を作り分けることができるのです。また、鉄は合金として使われることも多く、鋼・鋳鉄といったものがあります。

鋼とは、Steelとも呼ばれ、炭素含有量が約0.02〜2.1%の鉄合金です。熱処理によって、その機械的性質を調整することが可能です。また、鋳鉄は、炭素含有量が2.1%以上の鉄合金で、鋳造性に優れるが、脆く、鍛造には不向きな特性を持ち合わせています。鉄の主な機械的特性についてまとめると、以下のようになります。
| 性質 | 説明 |
|---|---|
| 引張強さ | 熱処理・合金化によって大きく変化。炭素量が増えると高くなるが脆性も増加。 |
| 延性 | 純鉄は非常に延性に富むが、炭素含有量が増すと低下。 |
| 硬度 | 焼入れにより急激に向上。ただし過度な硬度は脆性の原因。 |
| 耐食性 | 炭素鋼は錆びやすいため、合金化(ステンレス鋼など)や表面処理が必要。 |
鉄は非常に加工性が優れているため、様々な加工ができ、形を変えることで世に広まってきました。
次回は、実際に鍛冶屋で行われていた技法で鉄を加工した体験について紹介いたします。










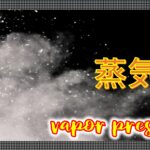







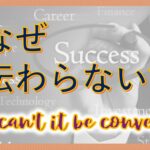
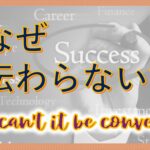
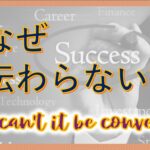
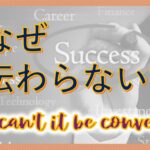








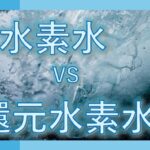




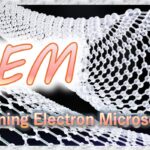
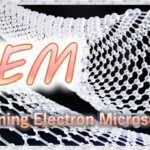
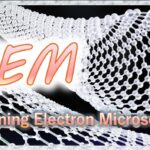








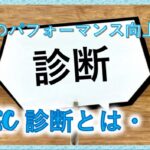
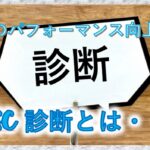




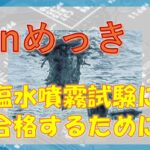
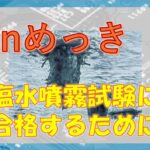
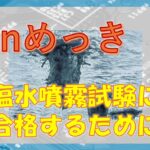












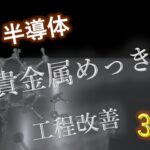
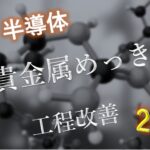
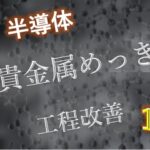
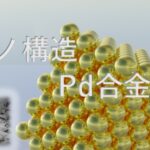
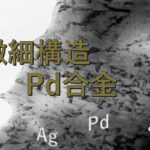

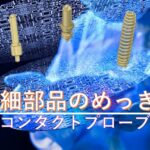














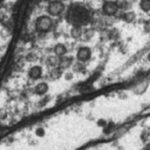

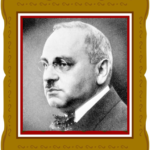




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
 FlabR(フラバー)について
FlabR(フラバー)について