前回は、鍛冶屋で行われていた鉄の加工技術について触れてみました。
今回は、実際に鍛冶屋で行われていた技法で鉄を加工した体験について紹介いたします。
実際に鉄を加工してモノを作ってみました。作ったものは、ペーパーナイフと壁掛けフックです。
工程は以下の通りです。
① 鉄の板材を適度な長さに切断する(長さ約300mm、幅約30mm、厚み約3mm)。切断方法は、鉄の板材を炭の中で赤くなるまで熱し、切断したいところをタガネとハンマーで叩き、V溝を作り、板厚を薄くする。その後、ヤットコを使用して、V溝部を折り曲げ、伸ばしを繰り返して疲労させ、板材を切断する。

② 切断した板材の加工部分を炭の中で赤くなるまで熱して、ハンマーで叩いて成形する。製作する形状になるまで、加熱と叩きを繰返し行う。

➂ 表面の保護をするために、墨で加熱してオイルに浸漬し、皮膜形成を行う。
④ FlabR社内にて、仕上がったものにめっきを実施。
ペーパーナイフは金めっきで仕上げてみました。

壁掛けフックはNiめっきで仕上げてみました。小さなフックのようなものは釘の役目をするものです(めっき未処理)。

この加工において非常に興味が湧いたのは、鉄の加熱具合を色を見て判断することでした。単に赤くなるというだけでなく、その色の違いが微妙に違ったりするのです。鉄を加熱したときの温度についてまとめてみました。
| 色の変化 | 温度 | 状態の説明 |
|---|---|---|
| 暗赤色 | 約 600~700℃ | 鉄がうっすら赤くなり始める。叩くには早い。 |
| 明るい赤色 | 約 800~900℃ | やや可鍛。軽い矯正は可能。 |
| オレンジ~黄赤 | 約 950~1050℃ | 最適な温度。 |
| 明るい黄色 | 約 1100~1200℃ | 柔らかく鍛造しやすい。過熱注意。 |
| 白色に近い | 約 1300℃ 以上 | 非常に柔らかくなる。酸化・焼き割れのリスク高い。 |
鉄の温度が約700℃以下(暗赤色)になると、鉄が硬くなり、延性が失われ、叩くと割れやすくなるため、再加熱が必要となります。炎の色や鉄の赤色状態、叩いた時の音、などを五感を通じて判断し、鉄で形作っていくことを昔からやられていたことに関心します。この伝統技法を肌で感じてやってみるのは非常に楽しい経験です。現代では、機械任せのようなところがありますが、その技術革新の元は、このような技法があってのことであり、理解することが重要だと感じます。
鍛冶屋は単なる「鉄を叩く職人」ではなく、金属の性質を深く理解し、その制御と応用を実践してきた高度な技術者といえるでしょう。歴史的には社会のインフラと軍事力を支える中核的存在であり、現代においても材料科学、機械加工、芸術表現の分野においてその知見は生き続けています。鍛冶屋の技術と知識は、鉄という素材の物理的・化学的特性と密接に結びついているのですね。
鍛冶屋の体験を通して得られた知識はたくさんありました。金属加工したものに表面処理を行うFlabRの仕事において、材料の加工技術を知ることは技術力の進展であり、今後も積極的にいろいろな分野にチャレンジしていこうというモチベーションになります。










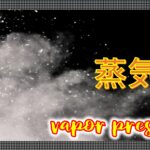







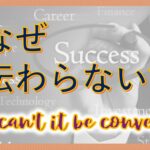
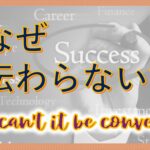
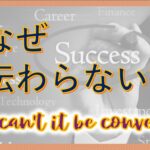
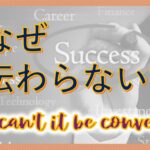








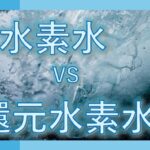




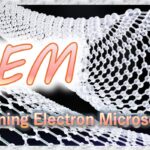
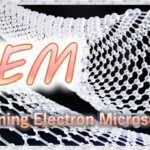
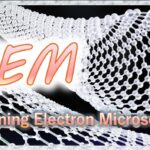








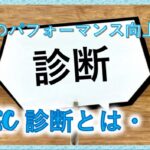
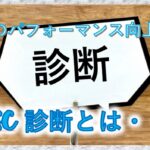




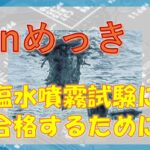
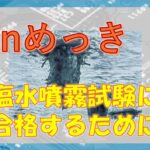
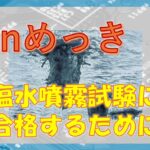












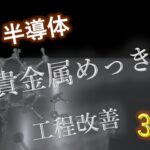
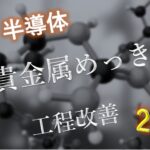
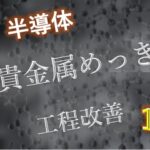
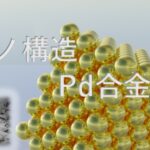
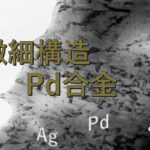

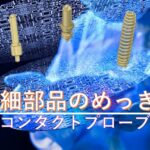














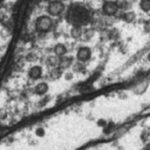

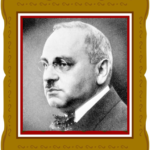




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
 FlabR(フラバー)について
FlabR(フラバー)について